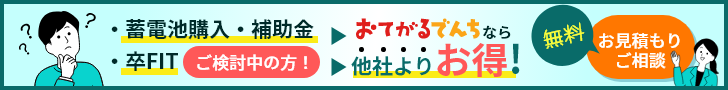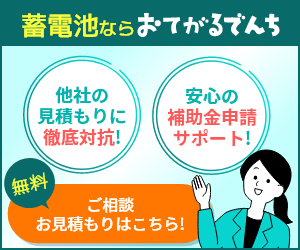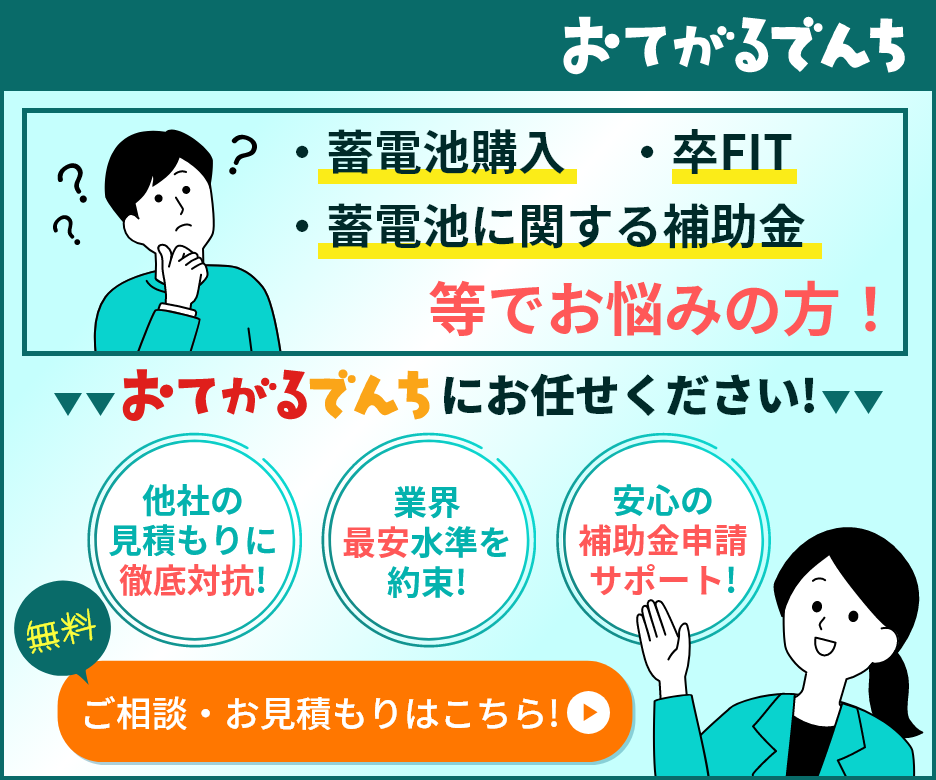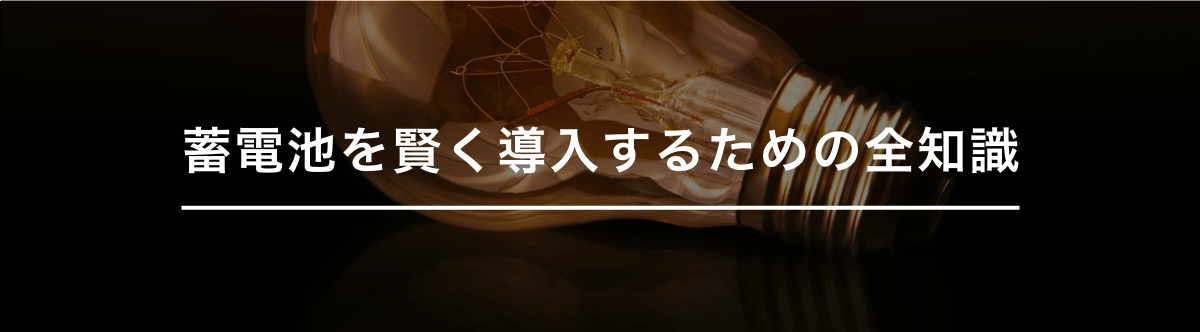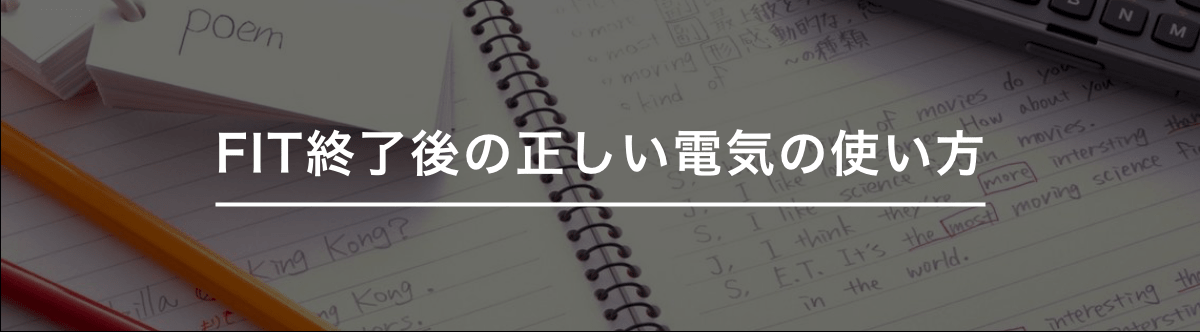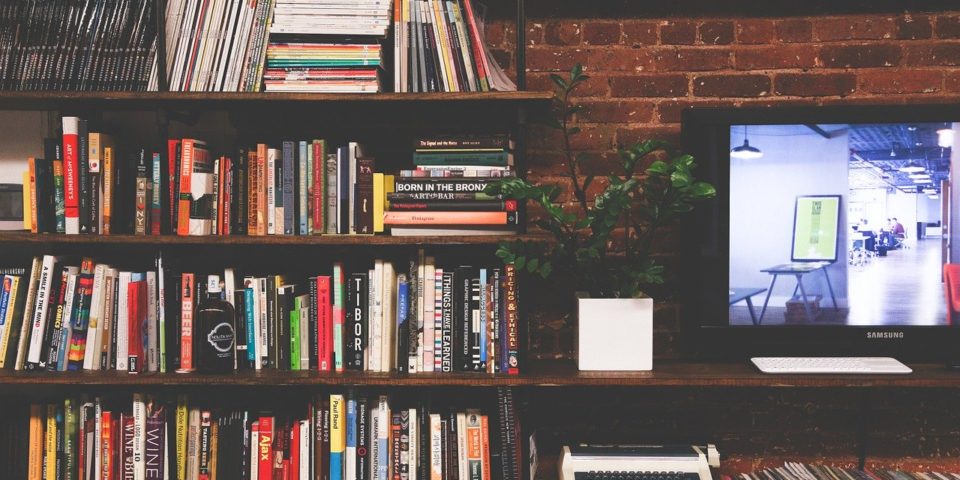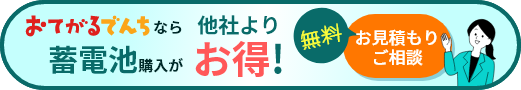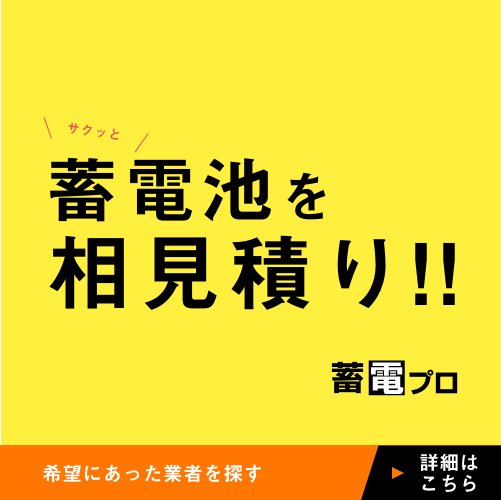リチウムイオン電池とは?特徴もわかりやすく解説!蓄電池を安全かつ効率的に運用するためには

スマートフォンやノートパソコン、電気自動車(EV)などのバッテリーとして、今や欠かせない存在となったリチウムイオン電池。近年、普及が進む家庭用蓄電池の多くに使用されているのもこのリチウムイオン電池です。
今回の記事では、リチウムイオン電池の詳細について解説していきます。また、リチウムイオン電池のメリットやデメリットについても説明していますので、蓄電池選びの参考にしてください。
リチウムイオン電池とは
リチウムイオン電池は、リチウムイオンが正極と負極の間を移動することで、充電や放電を行う二次電池です。電池と聞くと、使い切りタイプの乾電池を思い浮かべますが、リチウムイオン電池は、充電することで繰り返し使用できる二次電池に当たります。また、リチウムイオンは、アルカリ金属元素のリチウムが電荷を帯びた(イオン化した)状態です。つまり、リチウムイオン電池は、イオン化したリチウムの性質を利用することで充放電する、何度も使える電池であると言うことができます。
リチウムイオン電池の仕組み
それでは、リチウムイオン電池は、どのような仕組みで充放電を実現しているのでしょうか。
リチウムイオン電池は、プラチナを含む正極と、炭素材料である負極、さらにリチウムイオンを通しやすい電解質から構成されています。正極と負極は、互いに接触しないようセパレータ等で絶縁され、電解質を介して導電できるよう配置されています。充電時には電気の取り入れ口、放電時には電気の取り出し口としても機能します。
そして、充電時には、プラス電荷を持ったリチウムイオンが電解質を通って正極から負極へ移動。負極に到達したリチウムイオンと負極に流れ込んできた電子、さらに負極の物質が結合してリチウムを含む化合物を形成します。この一連の反応は、電気エネルギーを使用するからこそ起こります。
一方、放電時には、リチウムを含む負極の化合物が分解し、リチウムイオンは電解質を通って、電子は外部の回路を通って負極から正極に移動。正極に到達したリチウムイオンと電子、そして正極の物質が結合します。この反応は、負極と正極を結んだ外部の回路があれば起こるもので、同時に電気エネルギーを放出します。
つまり、リチウムイオン電池では、電気エネルギーを使用し、負極においてリチウムの化合物を形成することで充電を実現。負極におけるリチウムの化合物が分解するときに生じる電気エネルギーを利用することで放電を実現しています。
リチウムイオン電池のメリット
蓄電池に使用されている電池には、リチウムイオン電池のほか、自動車のバッテリーや産業用の定置型蓄電池に用いられている鉛蓄電池、乾電池型充電池に用いられているニッケル水素電池があります。以下では、鉛蓄電池やニッケル水素電池に比較した、リチウムイオン電池のメリット・デメリットを説明します。
リチウムイオン電池には、次のようなメリットがあります。
・エネルギー密度が高い
・電圧が高い
・自己放電が小さい
・電池効率に優れる
・長寿命
エネルギー密度が高い
リチウムイオン電池は、エネルギー密度が高い、つまり同じ重量やサイズで比べたときの蓄電容量が大きいです。重量換算では、鉛蓄電池の約5倍、ニッケル水素電池の約3倍、体積換算では、鉛蓄電池の約5倍、ニッケル水素電池の約4倍にも及びます。
電圧が高い
電圧が高いのもリチウムイオン電池の利点です。リチウムイオン電池の電圧は2.4V〜3.8V程度ですが、鉛蓄電池の電圧は2.0V、ニッケル水素電池の電圧は1.2Vと、リチウムイオン電池の2分の1、または3分の1ほどです。電圧は、電池を直列につなぐことで上げることができますが、リチウムイオン電池ではその必要性が低く、コンパクトな空間に収めることができます。
自己放電が小さい
自己放電は、蓄電池を使用せずに放置しておくと生じる放電現象です。リチウムイオン電池は、この自己放電が月10%以下と小さいことでも知られています。
電池効率に優れる
電池効率とは、放電で得られた電気量と充電に要した電気量の比で、電池効率が高いほど無駄なく電気を利用できます。リチウムイオン電池ではこの値が最大95%にも達するのに対し、鉛蓄電池では65〜80%、ニッケル水素電池では最大84%程度です。
長寿命
長寿命であることもリチウムイオン電池の利用を広範にしている要因となっています。鉛蓄電池とニッケル水素電池の蓄電容量が1500サイクル程度で減り始めるのに対し、現在のリチウムイオン電池では、3,600サイクル程度の充放電でも十分な蓄電容量を保ちます。
このように、リチウムイオン電池は、軽量性やコンパクト性、蓄電容量の大きさ、電気代節約に直結する優れた電池効率や小さい自己放電、寿命の長さなど、家庭用蓄電池が必要とする特徴を兼ね備えた蓄電池なのです。
リチウムイオン電池のデメリット
しかし、リチウムイオン電池には、以下のデメリットがあります。
・過充電・過放電に弱い
・異常発熱時の安全性
・価格が高い
過充電・過放電に弱い
リチウムイオン電池は、過剰に充電すると、急激に劣化して故障することがあります。場合によっては、破裂・発火することがあります。逆に、充電が切れた状態で放置し続け、過放電状態となると、蓄電容量が急激に低下し、電池としての機能を果たせなくなることがあります。異常発熱することもあり、事故につながる可能性があります。
そのため、リチウムイオン電池を用いる機器には、過充電や過放電を回避するための機能が備わっています。ですが、過充電・過放電の回避機能にも電気を必要としますので、過充電はともかく、過放電の完全な対策は難しいです。なぜなら、電気を供給できない状態で蓄電池を長期間放置すると、自己放電によって過放電状態になってしまうからです。
異常発熱時の安全性
また、リチウムイオン電池は、異常発熱を起こすことがあり、最悪の場合は破裂・発火・爆発を引き起こすことがあります。この事故は、そのほとんどがモバイルバッテリー用途のリチウムイオン電池で発生したものです。ですが、衝撃や生産時の欠陥が原因であるため、家庭用蓄電池においても全くないとは言い切れません。特に、地震後などに使用する場合には、注意が必要です。
価格が高い
価格が高いこともリチウムイオン電池のデメリットです。2012年における、定置型蓄電池に使用されるリチウムイオン電池の価格は20万/kWh、鉛蓄電池は5万/kWhと、かなりの価格差がありました。なお、ニッケル水素電池は、定置型蓄電池に使用されないため比較対象としていません。
その後、リチウムイオン電池の価格下落が進み、現在は価格差も小さくなってきています。リチウムイオン電池の価格は、2015年には13万/kWh程度(蓄電池全体としての価格は20万/kWh程度)まで低下。2018年には10万/kWh程度にまで下落しました。しかしこの傾向は、長くは続かないと予想されます。スマートフォンや電気自動車などの急速な普及により、リチウムイオン電池の需要が高まっているため、価格は上昇に転じると見られています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
家庭用蓄電池に使用される蓄電池は、今やほとんどがリチウムイオン電池です。そのため、リチウムイオン電池の特徴を知っておくことは、安全かつ効率的な蓄電池の運用に役立つでしょう。
また、リチウムイオン電池の価格についてもご紹介しました。蓄電池として販売される際には、紹介した価格に周辺機器や工事費なども上乗せされます。ですが、リチウムイオン電池の価格やその推移を知っておけば、きっと蓄電池選びの参考になります。